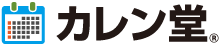毎年、夏になるとそろそろお盆の時期だなぁと思いますが、そもそもお盆ってなんだろう?
あまり深く考えたことがなく、気になったのでお盆について調べてみました。
目次
1.お盆ってなに?
日本の伝統的な行事で、先祖の霊を迎え、供養するための期間です。正式名称は、盂蘭盆会(うらぼんえ)と言います。語源はサンスクリット語のウランバーナ、もしくはウラバンナ(逆さに吊り下げられた苦しみ)です。
通常お盆は、8月中旬に行われますが、地域によっては7月に行われることもあります。
お盆の時期
地域によってはお盆の時期が異なり、新盆(7月)と旧盆(8月)の2つになります。
○新盆は、東京(多摩地区の一部を除く)、函館、金沢の旧市街地などで行われています。本来、お盆は7月15日に行われるのがふさわしいとされ、新暦にのっとって行われているのが新盆です。
○旧盆は、東京と一部地域を除く、ほぼ全国で行われています。8月15日を中心とした「8月13日~16日」の期間に行われるのが一般的です。お盆の時期がずれた理由は諸説ありますが、7月半ばの時期は農家の人々が農作業に追われて忙しく手が回らないため、旧暦のお盆の時期に近い8月15日を中心にお盆が行われるようになったそうです。
2.お盆はどのように過ごす?
精霊棚の準備
精霊棚(しょうりょうだな)・盆棚(ぼんだな)と呼ばれる、お盆のお供え物を飾るための棚を置きます。飾り方はそれぞれのご家庭によって異なりますが、ほおずき・夏の野菜や果物・そうめん・水の子・ミソハギの花・精霊馬などを飾ります。
精霊馬は、ご先祖様が家を行き来するための乗り物に見立てて作ります。行きは早く来られるようにキュウリで馬を、帰りはゆっくり帰ってもらうためにナスで牛を作って飾ります。
精霊馬はご先祖様の乗り物として作ったものなのでお盆が終わったとは食べずに処分しなければいけません。

お墓参り
お墓参りはお盆の期間中であればいつ行っても問題ありません。ですが、8月13日のお盆初日にお墓参りをされる方が1番多いです。地域によって異なりますがお盆の中日にお墓参りをする場合もあり、留守参りといいます。8月16日の最終日に、ご先祖様が無事に帰れますようにとお墓参りをする地域もあります。
お墓掃除をご先祖様をお迎えする前日までにしておくのが理想ですが難しければお墓参りの際でも大丈夫です。
迎え火・送り火
迎え火は、1年に1度帰省するご先祖様の魂が迷わぬように目印を示すことが目的です。迎え火は新暦か旧暦のどちらかのお盆初日である13日に焚くことが多いです。17:00~19:00頃が適切だといわれています。
送り火は、新暦か旧暦のどちらかのお盆最終日である16日におこないます。ご先祖様の霊が無事にあの世に戻れますようにという願いが込められています。送り火というと、京都の五山の送り火が有名です。ご先祖様を送り出すと同時に、京都の人々にとって大切な伝統行事であり、毎年多くの観光客も訪れる一大イベントとなっています。他にも、長崎県と佐賀・熊本の一部地域で行われる、精霊流し(しょうろうながし)などが有名です。精霊をあの世へ送り出すために、供物をわらや木で作った舟に乗せて川や海に流します。

3.お盆の時期にやってはいけないこと
川や海へいくこと
地域によっては、ご先祖様の魂は海や川に戻るため霊に足を引っぱられるという言い伝えがあります。
実際は時期的にクラゲがいるためクラゲに刺されてしまったり、台風の影響を受けての高波や土用波による水難事故などが考えられるため、避けた方がよいでしょう。
結婚式などのお祝い事
お盆はご先祖様を供養する期間なのでお祝い事はなるべく避けるのが無難です。
生き物の命を奪うこと
お盆の期間は、不殺生戒(ふせつしょうかい)とされており、生き物の命を奪うことが禁じられています。 そのため釣りや虫捕りであっても、殺生にあたるためよくありません。
4.お盆についてのまとめ

お盆は、ご先祖様に感謝の気持ちを示す大切な時期だと思います。日本の伝統的な行事であるお盆を通して、家族が集まり、お墓参りをしたり、精霊棚にお供え物をしたりすることで、自分たちがどれだけ先祖に支えられてきたかを考えることができますね。
また、お盆は「今ある生活に感謝する時間」でもあると思います。日々忙しく過ごしていると、つい忘れがちですが、ご先祖様が築いてくれたものに感謝し、今の自分たちがどれだけ恵まれているかを振り返ることは大切なことです。そうした感謝の気持ちが、家族や親しい人たちとの絆をさらに深める手助けになると思います。
※本コンテンツは、名入れカレンダー専門店カレン堂(運営:シティライフ株式会社)スタッフが独自に調査しまとめた内容となります。最新の情報などと多少の差異がある場合がございますので、何卒ご了承くださいませ。